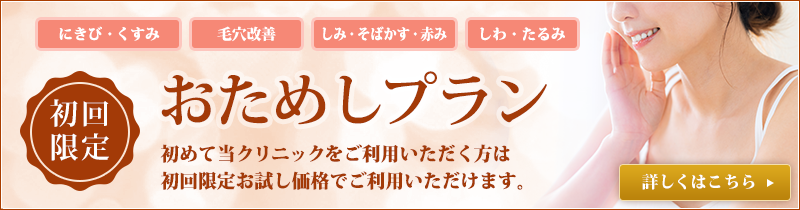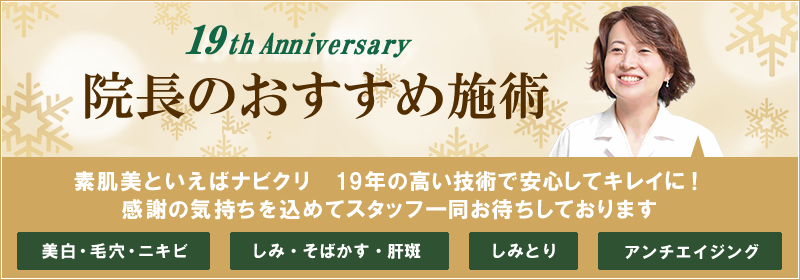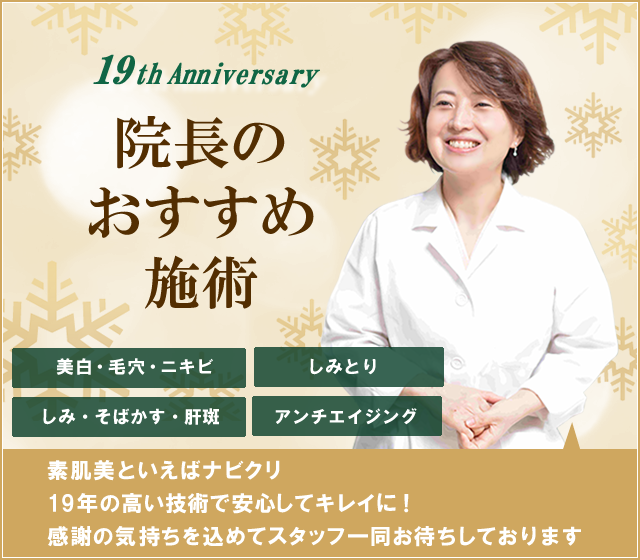皮膚・皮膚疾患の四方山話1-1 -アトピー性皮膚炎とは何かー

皆さん今日は! 南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。今日は、先日お知らせしましたように、アトピー性皮膚炎について解説したいと思います。
アトピー性皮膚炎は、皆さんご存知の方も多いと思いますが、正確にとなると如何でしょうか。多分、“皮膚病で、皮膚が痒くなって、なかなか治りにくい病気”といった受け止め方をなさる方が多いのではないでしょうか。確かに、症状からいうと、皮膚が赤くなって、痒く、“がさがさ”したり“じくじく”したりする病気です。この病態(病気の状態)は昔からよく知られていましたが、戦後1960年ごろから急速にその数が増えてきました。そして、それは現在でも続いています。その原因については、後にお話したいと思います。
さて、この病態の特徴は痒みが強いということです。罹った人は昼夜を問わず引っ掻いたりします。この痒みが何故強いかということも後で説明します。幼少期に多く、以前は小学校に上がるまでに自然に治るとされていましたが、最近は、成人になっても病状が治まらず、長く苦しむ例も少なくありません。この辺の経緯についても参考データーを後でお示ししたいと思いますが、皮膚科領域でも手を焼く、扱いの難しい疾患の一つなのです。
その理由は、この病態の発症(症状が出ること)に人間が持っている免疫防御機能の個人差が大きく関係していること、また原因が一つではない、つまり幾つかの病気の総称名である可能性があること、そして、発症の引き金になる因子が多数で、周囲からなかなか除去できない条件下にあること等が挙げられましょう。このことはアトピー性皮膚炎の根本問題なので、これから詳しくお話していきたいと思います。
しかし、巷を見ますと、書店には現在でも“簡単”に対処できそうな魅力的題名の書籍も多数並んでいますし、以前は、どの朝刊にもすぐ“治る”ことをほのめかす広告も多く見かけました。しかし、この病気が実は季節柄間もなく大勢の人が悩むと予想される“花粉症”や“喘息”と親戚の病気だということを知っている人は意外に少ないのではないでしょうか。そうなのです、正確に言いますと杉の花粉が原因で起きているアトピー性皮膚炎の患者さんも多いのです。また、“喘息”がよくなると“アトピー性皮膚炎”が悪化すると訴える患者さんも少なくありません。また、最近は、“アトピー性行進”、つまり最初に“アトピー性皮膚炎”が来て、次いで“気管支喘息”が来て、最後に“アレルギー性鼻炎”の“行進”が来る、ということを言い出す研究者もいます。ただ、アトピー性皮膚炎は、正直なところ現在なお明確にされない面も多数残しています。そこで、このブログでは、私自身が頭に描いているアトピー性皮膚炎について、興の赴くまま話してみたいと考えています。従って、或る意味では独断と偏見を交えた話になるかも知れませんが、どうぞご容赦ください。
このお話しの続きは次回にいたします。お楽しみに。