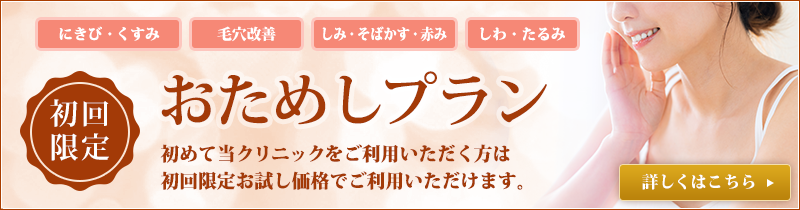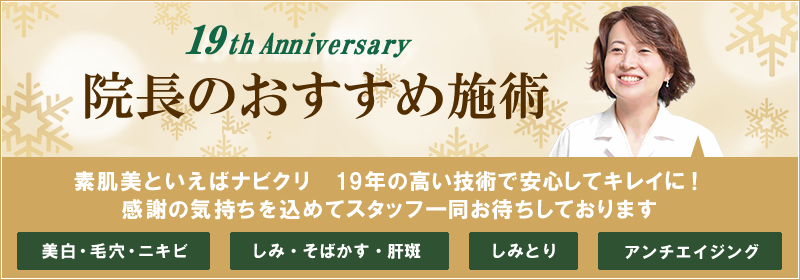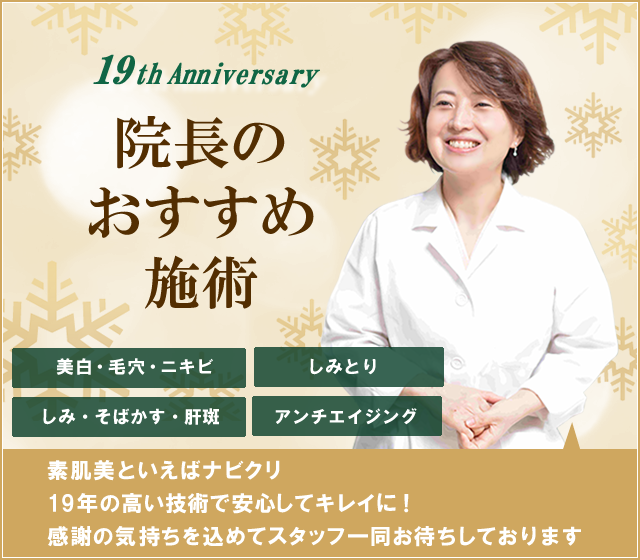皮膚・皮膚疾患の四方山話 3-2 -獲得免疫とアトピー性皮膚炎ー
 皆さん今日は!南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。前回は人の免疫防御機構の一部をご説明させていただきました。今回はその中のアトピー性皮膚炎の発症と深く関係すると考えられている“獲得免疫”の話をさせていただきます。
皆さん今日は!南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。前回は人の免疫防御機構の一部をご説明させていただきました。今回はその中のアトピー性皮膚炎の発症と深く関係すると考えられている“獲得免疫”の話をさせていただきます。
この“獲得免疫”は以前生体に侵入したことのある外敵異物が、再び同じ生体に再侵入しようとする際に起こってくる免疫防御力発揮の過程を指す、ということは前回お話しいたしました。つまり、“顔見知り”の外敵異物の防御方法ですが、これは更に2つに別けて考えると理解しやすいと思います。
その一つは異物(抗原)、これは多くは蛋白質、或いはその一部であるペプチドと呼ばれるもので、必ずしも生きた細菌や、ウイルスでなくても構いませんが、それが人体(宿主)に侵入しますと、人はそれが何であるかを知り、それに合う、即ち“特異的”な、“免疫グロブリン”という蛋白質(抗体)を作り出してその侵入、拡大を阻止しようとします。つまり、抗体がその異物(抗原)を捕捉、それを凝集、或いは沈降させ、貪食細胞の力を借りてそれを無害化し、体外に排除しようとするのです。
この反応は“液性免疫”と呼ばれ、前述のアトピー患者での血中“レアギン”、即ち“免疫グロブリンE” が増加するのも、その範疇に属した変化というわけです。つまり、“アトピー”と呼ばれる“喘息”や“枯草熱”は、表現型、つまり実際の所見としては、“液 性免疫”に異常が見られる疾患群と言っても良いでしょう。ただ、この防御能には限界があって、宿主の身体の中に入った異物(抗原)でも、細胞外にあるものの排除には働きますが、細胞内に取り込まれた異物を除去する力はありません。それには次に述べる細胞性免疫が主役を演じることになります。ここでは“皮膚炎”の話を取り上げますので、“液性免疫”については後日説明したいと思います。
そ こで、もう一つの“獲得免疫”である細胞性免疫の話しに移りますが、“皮膚炎”はその代表とされるものです。つまり、その際、免疫防御の主役となるのは、 “免疫グロブリン”ではなく、リンパ球という“細胞”がそれに当たります。即ち、リンパ球が異物抗原を覚えていて、それを抗原特異的に(その抗原に限って)攻撃するので、“リンパ球仲介性応答”或いは“細胞性免疫”と呼ばれています。
これは、侵入微生物が、結核菌やらい菌、或いは真菌であった場合、菌の外壁が蛋白分解酵素に抵抗性の高い(蝋等の)構 造でできているため、簡単には死滅させられません。そこで、この獲得免疫の一手段“細胞性免疫”が使われるわけです。これは細胞内に隠れた微生物を、リン パ球で細胞ごと攻撃し、標的となるそれを細胞外に曝露させ、抗体や別の貪食細胞で処理しようとするものです。この仕組みでは、標的を特異的に攻撃するた め、リンパ球は何が貪食されたか、標的となる異物(抗原)を正確に読み取る必要があります。
そこで、その方法として、貪食細胞が食べた異物(蛋白乃至ペプチド)の一部(或るアミノ酸配列)を細胞表面に旗のように掲げ(抗原提示)、それをリンパ球(ヘルパーT細胞)が受容体を通して確認(抗原認識)します。そして、次に同じ標識を持った細胞に出会うと、攻撃するのです。ただ、その提示物は蛋白そのものだけでなく、脂質や、ハプテンと呼ばれる無機の化合物も、蛋白やペプチドの助けを借りて、提示することができます。
さて、“細胞性免疫”ですが、例えば、ツベルクリン反応の陽転化は、この免疫現象の過剰表現の一例です。これは結核菌に感染しますと菌体の一部が認識され、その後2、3週間以上たって、菌の精製蛋白溶液(ツベルクリン液)が皮内に注入されますと、それが抗原として再認識されるため、リンパ球の標的となって、注射部の発赤や浸潤、浮腫場合によっては水疱の形成を見る、という現象です。つまり、結核菌に対する細胞性“免疫が獲得されている”ことを示すものです。
“皮膚炎”の場合もそれと同等な機転が進行し、“炎症”として我々はそれを認識します。この機転をもっと詳しく説明しますと、外界から皮膚への侵入異物(抗原)は、皮膚表層にいる“樹状細胞”、これは抗原提示能の高い貪食細胞で、“抗原提示細胞(APC)”とも呼ばれ“ランゲルハンス細胞”がその代表ですが、これがそれを捕捉、貪食して、その後その情報を持って、近くにあるリンパ節に移動します。そこで上述の抗原提示をし、そこにリンパ球(ヘルパーT細胞)がきて、接触、自らの受容体を通じて、この抗原と提示装置複合体を認識して、情報を受け取ります。この情報を得たリンパ球は、数を増やし、後で同じ異物(抗原)が、 多くは外から、表皮に入りますと、既に“顔見知り”となっている、つまり“獲得免疫”ができているので、それを察知して表皮内に侵入し、細胞表面に同一抗 原を提示する細胞を見つけると、それを標的として、サイトカインと呼ばれる小型の糖蛋白を放出して攻撃し、排除しようとします。その結果、皮膚は赤くなっ て(血管拡張)、ぶつぶつ(浮腫)が起こり、神経を刺激し(痒み)、これが皮膚炎です。つまり“獲得免疫”の一つ“細胞性免疫応答”の定型です。
要 するに、前回少し説明しました第一型の獲得免疫、即ち“液性免疫”は、免疫グロブリンを使う“細胞外にある抗原”の排除が特徴の応答ですが、これに対して 第二型の獲得免疫、即ち“細胞性免疫”は、標的細胞を壊して“細胞内にある異物”を排除しようとする機転で、まったく異なっています。つまり、“皮膚炎” は主に表皮細胞がリンパ球の標的となって攻撃を受ける反応なので、“細胞性免疫”、即ち第二型の獲得免疫に属すことになります。
さて、この“細胞性免疫”が正常人において発揮された場合、通常“かぶれ”(接触皮膚炎)とか、ツベルクリン反応等に見られるような、24時間から48時 間を反応ピークとする所謂“遅延型過敏症”の形をとるのが特徴です。アトピー性皮膚炎も“皮膚炎”ですから、同じような機転が起こっているはずですが、で は、その機転のどこがアトピー、“変わっている”のでしょうか。次回はそうした事項について言及してみたいと思います。