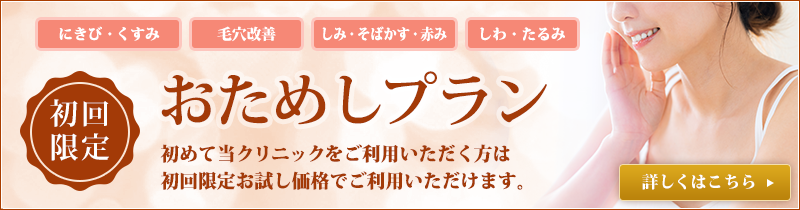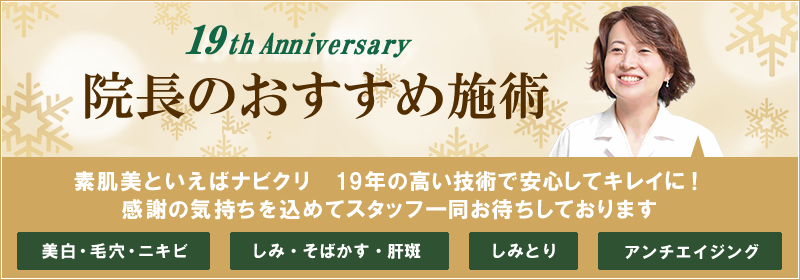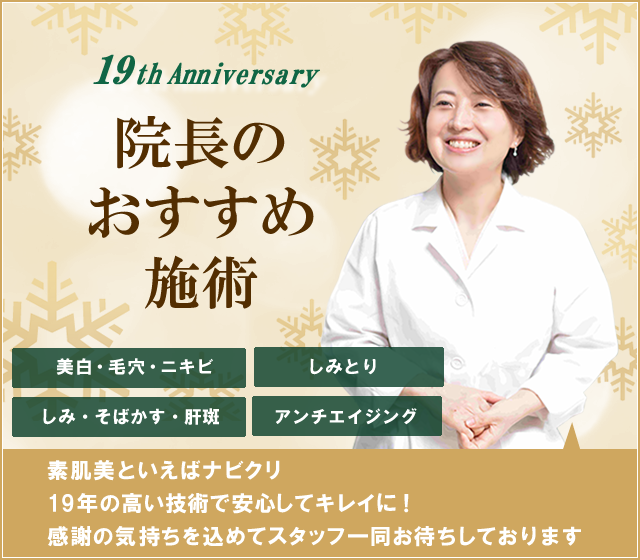皮膚・皮膚疾患の四方山話4-1 -アトピー性皮膚炎は普通の皮膚炎とどう違うのかー
 皆 さん今日は! 南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。前回は人の持つ自然免疫、獲得免疫について、アトピー性皮膚炎との関連でお話しまし た。今回は“普通の皮膚炎”と“アトピー性皮膚炎”とは同じ皮膚炎でもどこが、組織学的に、細胞レベルで、また分子の領域で違うのか、その当りのことを述 べてみたいと思います。
皆 さん今日は! 南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。前回は人の持つ自然免疫、獲得免疫について、アトピー性皮膚炎との関連でお話しまし た。今回は“普通の皮膚炎”と“アトピー性皮膚炎”とは同じ皮膚炎でもどこが、組織学的に、細胞レベルで、また分子の領域で違うのか、その当りのことを述 べてみたいと思います。
ここからは、かなり専門的な話しになりますが、できるだけ正しく説明しようとしますと、どうしても難しい表現になります、どうぞご容赦ください。
さ て、アトピー性皮膚炎は、主として獲得免疫の機転に、普通の免疫応答とは違う“顔”を見せるのが特徴である、というお話は既にいたしました。その顔の一つ は“液性免疫”として血中の免疫グロブリンが増加するのですが、正常人に見られる一般の炎症ではその際増えるのは免疫グロブリンG(IgG)が主で、それによって例えばウイルス等の侵入異物は血中から容易に排除できるのが特徴です。
これに対して、アトピー性皮膚炎では、他の喘息やアレルギー性鼻炎と同様に、なぜか専ら“免疫グロブリンE(IgE)が増加”します。これはIgGと違って侵入異物を簡単に処理する力はないようで、そのため病態は遷延しがちになります。こうした血中のレアギン、即ち免疫グロブリンEの増加は、CocaとCookeが提唱した“アトピー”の概念に一致し、免疫アレルギーという観点では、“I型 アレルギー”、あるいは“即時型過敏症”とも呼ばれ、喘息やアレルギー性鼻炎と同様に、症状としては肥満細胞からのヒスタミンを主とした化学伝達物質の放 出に起因する機転を特徴とするものです。従ってこの点では“アトピー性皮膚炎”を“アトピー”と位置づけるのになにも問題はないように思われます。
しかし、問題は“皮膚炎”で、この免疫応答は既に前回にお話いたしましたように“細胞性免疫”です。これは過敏症の概念では、反応のピークが24から48時間後に起こるのを特徴とする“遅延型過敏症”に位置づけられ、一般には“IV型 アレルギー”の範疇に入る病態と受け止められています。この変化は、主にリンパ球が抗原やそれを提示する標的細胞に襲い掛かって、それ等を損傷する“サイ トカイン”と呼ばれる小型糖タンパクを放出する、ことに基づいて発生するので、喘息やアレルギー性鼻炎で見られる、主として“ヒスタミン”の放出から齎さ れる反応とは異なる所から“アトピー”として取り扱っていいかどうか議論が生じました。
では何故アトピー性皮膚炎では遅延型過敏症なのに即時型過敏症に見られるようなIgEの増加が起こるのでしょうか。このことについては20年 以上前までは、よく分かっていませんでした。アトピー性皮膚炎の皮膚病変、即ち“皮膚炎”部を肉眼で見ますと、急性期に見られる変化は、既に述べましたよ うに、皮膚表面は赤く発赤し、ぶつぶつ細かく盛り上がり、“水”を持ってじくじくし、一部では乾燥してがさがさし、痒みがあります。これは“かぶれ”と呼 ばれる“接触皮膚炎”や普通の“湿疹”と殆ど一致した変化で、両者は肉眼的には容易には区別できません。同様に、その部分を顕微鏡でみても、表皮に強い細 胞間浮腫があり、表皮、真皮にリンパ球を主とする細胞浸潤が見られる点を含め、両者は殆ど同じ像を示します。ただ、アトピー性皮膚炎の方が、好酸球と呼ば れる白血球が多いのが目立つぐらいの違いでしょう。また、慢性に経過した場合でも表皮は厚くなり慢性湿疹のそれと簡単には区別できません。
と ころが、この皮膚の病変組織内の、細胞同士が一つのコミュニケーション手段として出している、先にご説明しました“サイトカイン”と呼ばれる小型の糖タン パクや、それを受け止める細胞表面の“受容体”や“接着因子”と呼ばれる分子の種類は、実は両者間には大変な違いが起こっていることが分かってきたので す。普通の“皮膚炎”/“湿疹”も“アトピー性皮膚炎”も、同じ“皮膚炎”、すなわち“遅延型過敏 症”であるにも拘らず、両者は様々な違いを見せます。しかし、その秘密を解く鍵は実はここにあったのです。ここ十数年前ごろから臨床免疫学分野では急速な 進歩がみられ、次第にそのことが明らかにされてきました。そこでようやく“アトピー性皮膚炎”は“アトピー”であるかないかの議論に終止符が打たれること になりました。
その具体的な機転については、説明が長くなりますので次回に譲りたいと思います。