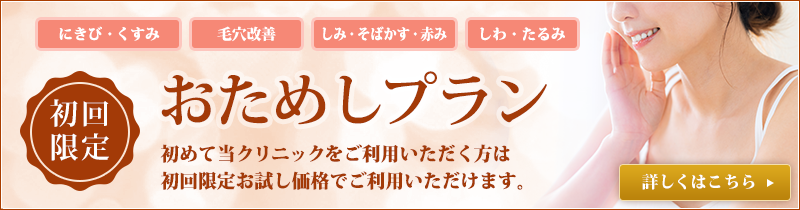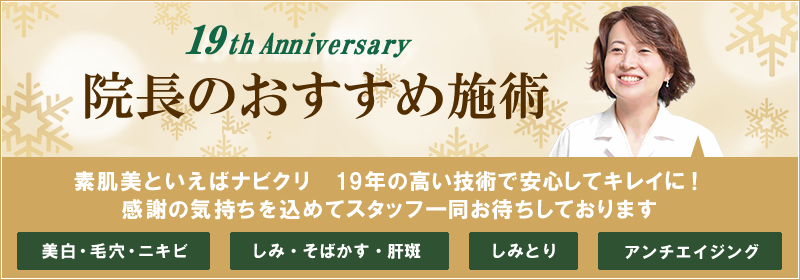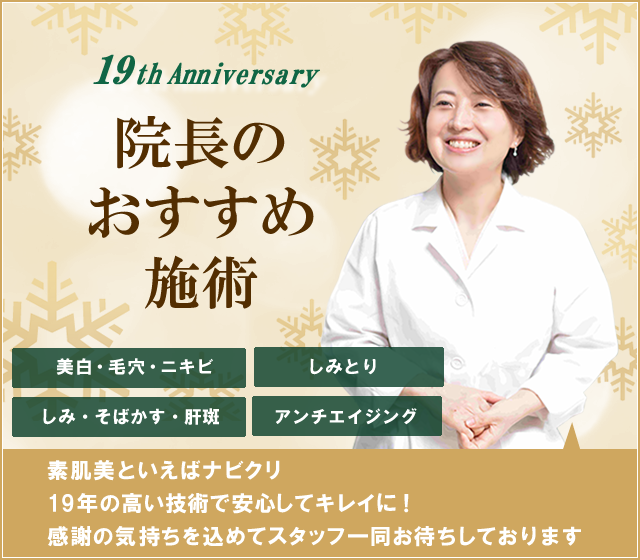皮膚・皮膚疾患の四方山話 4-3 -アトピー性皮膚炎のTh細胞は特定の抗原にのみTh2優位に応答するー
 皆さん今日は、南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。
皆さん今日は、南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。
話 がかなり理屈っぽくなりましたので、退屈とお感じの皆様方も多いかもしれません。しかし、この話しはもう少しで終わりにしたいと思いますので、なお若干の ご辛抱をお願いしたいと思っております。さて、前回は“アトピー性皮膚炎”に罹患した患者さんと、普通の正常人の方々のヘルパーT細胞の持つ“或る特定の異物抗原”に対する反応性に違いがあるという話をいたしました。今回は、その違いについてもう少し補足した説明をしたいと思います。
繰り返しますが“アトピー性皮膚炎”の患者さんのTh細胞は、“ヒョウヒダニ”とか、“スギ花粉”とかいった“特定の抗原”に対して、インターリューキン4(IL-4)やIL-5 といったサイトカインを放出するTh2型の応答で答えるのが特徴です。しかし、アトピー性皮膚炎の患者さんの、別のTh細胞は、抗原がその“特定の抗原以外”であったり、また“それ以外の抗原を提示する”標的細胞であったりすると、Th2型ではなく、普通の、即ち正常のTh1型の応答で対応する、ということはご存知でしょうか。
実は、そこが大変重要で面白いところなのです。例えばアトピー患者の血液から採取されたヘルパーT(Th)細胞は、破傷風トキソイドやカンジダ(酵母菌)に対しては、何故か正常人と同様のガンマー・インターフェロンを出して応答するのです。つまり、同一個人のTh細胞が、認識抗原の違いによって、Th2型で応答するものもあれば、Th1型で対応するものもあるということです。なお、蛇足ですが、普通の正常人はヒョウヒダニやスギ花粉に対しても、一貫してTh1型で応答することはいうまでもありません。ただ、アトピー性皮膚炎患者では、何故抗原の違いによって、実働する“効果細胞”の種類が異なるのか、その機転については現在なお明らかにされていません。このことは、真に当然のことでして、もしすべての異物抗原に対してTh 2型でしか応答できないのであれば、その場合は恐らくその人は生存できないでしょう。
このことは、マウス(ネズミ)の実験からも類推されます。SCIDマウスという免疫応答に障害のある品種がありますが、このマウスは先天的にライシュマニアという原虫の感染に抵抗力が弱く、他種のマウスはこの原虫が皮膚に接種されてもTh1型応答によって、この原虫(抗原)を接種部に限局させ、やがて体外に排除して健常体に戻りますが、このSCIDマウスはそれが出来ずTh2型でしか応答しないため、接種された原虫は増殖して全身に広がり、やがて衰弱して死亡してしまいます。つまり、細胞内抗原に対してTh2型 でしか応答できない動物では、その抗原を限局させ、分解して体外に排除するという機能に欠陥がある、ということです。このことは、アトピー性皮膚炎患者に おいて、病変が遷延し中々治癒しないという原因に、こうした機序が関わっている、ということを強く想起させます。そういう事例がありますのでご理解頂ける と思います。
さて、アトピー性皮膚炎患者がTh2型で応答するこの“特定抗原”は数多く知られていますが、日本では、先程お話した“ヒョウヒダニ”や“スギ花粉”が多いようです。それはCoca とCookeが“アトピー”疾患の代表と考えた“気管支喘息”(ヒョウヒダニ)や“花粉症”(杉花粉)の症状の引き金となる抗原と共通することは大変興味深いところです。恐らくこうした患者さんの“抗原”を提示する表皮“樹状細胞”が特別な性質を持っていて、“特定の抗原”、これは植物や動物の蛋白分解酵素が多いのですが、それを提示する際、認識するTh細胞がII型の応答をするように働くのではないでしょうか。
そういうことで、既にお話いたしましたが、同じ“皮膚炎”でも正常人が“どんな抗原に対しても”“かぶれ”で見られるようなTh 1型で反応するのに、アトピー性皮膚炎の患者さんは“或る特定の抗原”に限ってTh 2型で応答するところに、何度もいうようですが、特徴があります。また、その体内に入った“特定の抗原”の除去は十分でなく、そのための“皮膚炎”による痒みの他に、血中にその抗原に特別に反応する免疫グロブリンE(IgE)が 増加します。それが肥満細胞表面にくっ付いて、そこに抗原が再接触した場合、ヒスタミンの遊離が齎されます。それが更に痒みを増強させ、そのため掻破を繰 り返すということになります。そこで、もしこの抗原の侵入が止まず、それから回避できないとなると、皮膚の変化は長期化し、これが悪循環する、ということ で独特な臨床像が形成されることになるものと思われます。そういうことで、やはり“アトピー性皮膚炎”は“アトピー疾患”のカテゴリーに入る疾患というこ とになろうかと思います。
次回は、アトピー性皮膚炎においては、Th細胞の抗原の認識の違いが、Th1やTh2を誘導すると考えられますから、それをよりよく理解するために、もっと突っ込んだ抗原提示の仕組みや、それに重要な役割を果たす抗原提示細胞(APCs)、即ちその多くは“樹状細胞”と呼ばれるものですが、その種類や、そのアトピー性皮膚炎における違い等について、もう少し補足説明をして、それからアトピー性皮膚炎の示す諸々の特徴についてお話ししていきたいと思います。