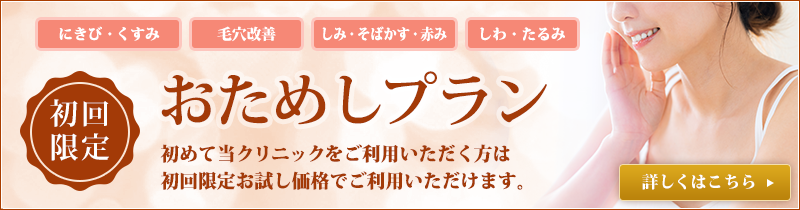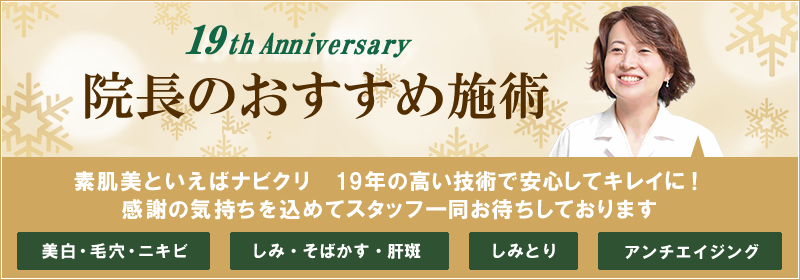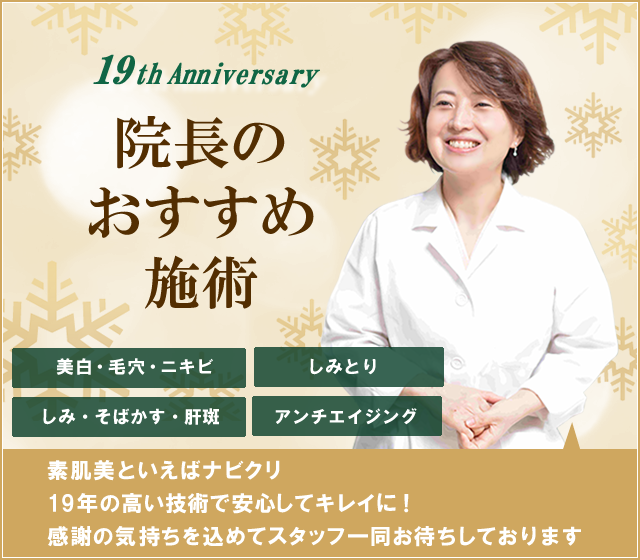皮膚・皮膚疾患の四方山話5-2 -抗原提示細胞(APCs)はリンパ節で抗原情報をTh細胞に伝える ―
 皆さん今日は! 南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。さて、前回までアトピー性皮膚炎の患者さんの示す免疫応答性は、普通の人とかなり違って(“アトピー”)いる、というお話をいたしました。そして、その原因は恐らく、皮膚表層部分に住んでいる抗原提示細胞(APCs)(antigen presenting cells)、一種の貪食細胞ですが、それが外からの侵入異物を捕捉し、それを分断、受動免疫ステップの第一歩として、その一部ペプチドを抗原としてヘルパーT細胞(Th細胞)に提示する。その提示の仕方が、通常人と違っているのではないか、という話しを申し上げました。そして、抗原の提示は、アトピー性皮膚炎患者の場合APCs細胞の抗原提示装置(蛋白)、MHCクラスII、それもHLA-DPとか-DQとか-DRに、主に提示されるということも説明しました。また、MHCクラスIIの構造、それを作る遺伝子のお話しもいたしました。また、それとは別に、それ等のAPCsは、アトピー性皮膚炎の患者の場合、抗原蛋白の一部(抗原決定基)が、もし以前捕捉したことのある“特定のペプチド”と分かれば“Th 2型”、“特定でない異物ペプチド”であれば“Th 1型”で反応するようにTh細胞を誘導する、それが特徴であると説明いたしました。ただ、何故抗原によってその差ができるのか、その機序については尚十分に分かっていないとも申し述べました。その後アトピー性皮膚炎におけるTh2優位性応答は、時間の経過と共にTh1型に変わる、つまり2相性であるという発表や、普通Th1型の応答を示すハプテン(単純化学物質で、それだけでは抗原性を発揮できない)を 繰り返し皮膚に塗布していると、アトピー性皮膚炎に似た病変を作る、という報告もあって、アトピー性皮膚炎の本態は、そう簡単に説明できるほど単純なもの ではない、と現在一般には受け止められてきています。ただ、この点については、私はもう少し補足説明をしなければいけないだろうと思っています。なお、こ の過程は結構複雑で専門用語が沢山出てきますので退屈な方はスキップして下さって結構です。
皆さん今日は! 南青山皮膚科スキンナビクリニック特別顧問の石橋です。さて、前回までアトピー性皮膚炎の患者さんの示す免疫応答性は、普通の人とかなり違って(“アトピー”)いる、というお話をいたしました。そして、その原因は恐らく、皮膚表層部分に住んでいる抗原提示細胞(APCs)(antigen presenting cells)、一種の貪食細胞ですが、それが外からの侵入異物を捕捉し、それを分断、受動免疫ステップの第一歩として、その一部ペプチドを抗原としてヘルパーT細胞(Th細胞)に提示する。その提示の仕方が、通常人と違っているのではないか、という話しを申し上げました。そして、抗原の提示は、アトピー性皮膚炎患者の場合APCs細胞の抗原提示装置(蛋白)、MHCクラスII、それもHLA-DPとか-DQとか-DRに、主に提示されるということも説明しました。また、MHCクラスIIの構造、それを作る遺伝子のお話しもいたしました。また、それとは別に、それ等のAPCsは、アトピー性皮膚炎の患者の場合、抗原蛋白の一部(抗原決定基)が、もし以前捕捉したことのある“特定のペプチド”と分かれば“Th 2型”、“特定でない異物ペプチド”であれば“Th 1型”で反応するようにTh細胞を誘導する、それが特徴であると説明いたしました。ただ、何故抗原によってその差ができるのか、その機序については尚十分に分かっていないとも申し述べました。その後アトピー性皮膚炎におけるTh2優位性応答は、時間の経過と共にTh1型に変わる、つまり2相性であるという発表や、普通Th1型の応答を示すハプテン(単純化学物質で、それだけでは抗原性を発揮できない)を 繰り返し皮膚に塗布していると、アトピー性皮膚炎に似た病変を作る、という報告もあって、アトピー性皮膚炎の本態は、そう簡単に説明できるほど単純なもの ではない、と現在一般には受け止められてきています。ただ、この点については、私はもう少し補足説明をしなければいけないだろうと思っています。なお、こ の過程は結構複雑で専門用語が沢山出てきますので退屈な方はスキップして下さって結構です。
さて、まず、抗原提示細胞(APCs)の種類とそれ等の行動についてお話しすることに致します。何度も申し上げましたが、皮膚には外界からの異物抗原の侵入を見張り、防ぐために、貪食機能の旺盛な細胞、貪食細胞(マクロファージとも呼ばれる)が、ほぼ均一の密度で分布していて、中には、互いに長い細胞質突起を伸ばして、互いに接触し、網目のような構造を形成しているものもいます。その代表が、既に述べた、表皮内に居住するランゲルハンス細胞(LCs)で すが、その他にも表皮直下の真皮に“真皮樹状細胞”と呼ばれる細胞が存在していて、抗原提示に大きな役割を果たしていることが最近明らかになってきまし た。これ等貪食細胞は多くは骨髄由来の細胞で、血管を通って皮膚に移住したものですが、貪食能の他に、何を貪食したか、それを他の細胞に知らせる能力にも 優れているものが多く、抗原提示細胞(APCs)とも呼ばれます。また、それ等の多くは樹枝状の長い突起を持つものが多く、樹状細胞(dendritic cells(DCs))とも呼ばれています。
さて、抗原の“提示”は、健常な人では、まず皮膚のAPCs(表皮のランゲルハンス細胞(LCs)と真皮樹枝状細胞(DDCs))が、抗原を受け取りますと、自らそれをリンパ球(Th細胞)に伝える(提示する)ために、共に皮膚から移動して、所属リンパ節(最近はdraining lymph nodesと呼ばれる)に向かいます。この移動は、殊にDDCsの場合結構速く8時間後既にリンパ節に到達すると言われています。一方、LCsはこれより遅く2、3日後にやや遅れて現れるようです。従来は、そこで、LCsが直接リンパ球(Th細胞)に情報を伝え、その結果、Th細胞は異物抗原が侵入してきたことを知り、自ら分裂して数を増やし、次にこの情報を提示する標的に遭遇すると、細胞傷害性サイトカインを放出して、標的を攻撃(免疫応答)する、とされてきました。つまり、抗原情報の仕込みですが、この機転は現在しばしばprimingと呼ばれています。これが所謂受動免疫応答の本態です。しかし最近では、この際のprimingはLCsやDDCsが直接行うのではなく、まず情報は一旦、元々リンパ節に居住していた別の樹状細胞(RLDCs)に伝えられ、この樹状細胞が直接Th細胞をprimingすることが分かって来ました。ただ、アトピー性皮膚炎患者の場合は、その他炎症を起こした表皮内に“炎症性樹状表皮細胞(IDECs)”と呼ばれる、更に別の樹状細胞がいて、数を増し、それがアトピーに見られる血中の抗原特異的IgE抗体の著明な増加に関与するとされています。そこで、実際にこの細胞が抗原提示にどう関わっているのか、また抗原提示のため所属リンパ節に移動するかどうかが問題ですが、それ等についてはまだよく分かっていないのが実情です。また、何故こうしたAPCsは抗原を捕捉し、その一部ペプチドを提示するために、わざわざリンパ節に移動するのか、その理由も分かっていません。いずれにしても、リンパ節における抗原提示は、こうした経過で、後の“反応細胞effector cells”であるTh細胞、多くはCD4+Th細胞ですが、に伝えられる訳です。
リンパ節はリンパ球の溜り場であり、リンパ球の生産工場でもありますから、周囲には沢山のリンパ球(Th細胞(主にCD4+細胞))がいます。それ等が次々と抗原提示細胞APCs(RLDCs)に接触してきて、その細胞表面の既にご説明いたしました、異なった提示装置(多くはMHCクラスII蛋白で、HLA -Dp、-Dq、-Dr等と呼ばれる)上にある、それぞれ異なった抗原ペプチドを、その度に認識して行くことによって完了します。 つまり、接触に際して、APCsによってこれ等Th細胞に片っ端から荷札tagが付けられるように、読み取り(抗原情報の受け渡し)がなされて行く訳です(私はTh細胞によってAPCsの抗原ペプチドがMHC装置と一緒に、食い千切られるのではないかと想像していますが)。この提示抗原ペプチドは様々ですので、接触するTh細胞へのtagも一つ一つ違っている筈です。
話しが長くなるので今回はここまでとし、次回にはその証拠としてAPCsによって表示され、Th細胞によって認識される抗原ペプチド(外来性の蛋白なので、その長さはアミノ酸10~15個が適当)は、接触するTh細胞ごとに違っている、つまり同じTh細胞でも、認識している抗原部分(抗原決定基)はtagが違うように、違うのだという話をしたいと思います。